最近、英検準一級を目指している個別指導の生徒(高1)にいろいろと面白い課題を出しています。
そのうちの一つが、「映画を使った英語学習」です。
このレベルになってくると、「英語で何かを楽しみながら勉強する」ということができるようになってきます。
その子はディズニーが好きで、ディズニープラスに加入しているらしいので、さっそく私も加入。笑
「毎週映画を2本観て、気になった表現をメモしてくる」という課題を出しました。英語音声・英語字幕です。
もちろん、私も同じ映画を観て内容を把握しておかないと、質問を受けても適切に回答できないので、生徒が「今週はこれを見ます」といったら、私も同じものをあらかじめ見ておくという、私も時間を吸い取られる方式の課題です。笑
でも生徒が楽しそうだからいいのです。
こういう課題の出し方は、個人塾だからこそできることですよね。
今週、生徒はマレフィセントを見てきました。
何度か見たことがあるお気に入りの映画らしいです。やはり初めての映画を英語で観るのはまだ少し難しいので、見たことがある映画を選ぶのは賢いですね。
かなり面白く、マイベストディズニー映画ランキングの上位に食い込んできました。
生徒からの質問で面白かったのが、マレフィセントがオーロラを呼ぶときの「Beasty」ってどういう意味ですか、というもの。
Beastyは、Beast(獣)に-yをつけて、小さくて可愛い感じを付与した言葉です。日本語でいえば、「野獣ちゃん」みたいな感じでしょうか。
私も、「なんでBeastyなんだろう」と思いながら観ていて、いまいち腑に落ち切らない感覚はありましたので、ChatGPTにも意見を聞きつつ、生徒と一緒に考えていました。
ちなみにChatGPTの答えは以下のとおりで、非常によくまとまっています(授業ではChatGPTとも英語で話していますので、下記はその和訳です)。
マレフィセントがオーロラをBeastyと呼ぶ理由
① 皮肉と苦々しさ
『マレフィセント』(2014)の序盤で、マレフィセントはステファン王に裏切られたことで深く傷つき、怒りに満ちています。彼女はオーロラに呪いをかけ、”Beasty(野獣ちゃん)” と皮肉を込めて呼びます。これは、本来「無垢で可愛い子」と呼ばれるはずの赤ん坊を、あえて反対の言葉で呼ぶことで、マレフィセントの捻くれた感情を表しています。この名前には、オーロラが裏切りの産物であり、呪われた子であり、マレフィセント自身や王国にとって危険な存在だという彼女の初期の認識が表れています。
② 感情的な距離と否認
“Beasty” というあだ名を使うことで、マレフィセントはオーロラとの間に感情的な距離を保とうとしています。本当は情が移りつつあっても、それを認めるよりも、あえて名前をからかう形で呼ぶ方が自分の心を守りやすいのです。しかし物語が進むにつれ、その呼び名のトーンも変化していきます。
③愛情と遊び心
物語が進むにつれ、”Beasty” は侮蔑的な意味から、愛情を込めたニックネームへと変わっていきます。マレフィセントがオーロラを深く大切に思っていることが明らかになるにつれ、この呼び方はまるで「ぶっきらぼうなおばさんが可愛い姪っ子をからかう」ような、微笑ましい表現に変わります。
④役割の逆転
興味深いことに、かつて「眠れる森の美女」の物語では、マレフィセントこそが “野獣” や “怪物” のように描かれていました。しかし、彼女がオーロラを “Beasty” と呼ぶことで、暗に役割が逆転しています。今やオーロラのほうが隠された力を持ち(マレフィセントの心を変える力)、マレフィセント自身は「誤解された存在」として描かれているのです。
ChatGPTの意見も参考にしつつ、生徒と少し話していて、はたと気が付きました。
「あれ、BeastyってBeautyのuをsに変えただけじゃん!」と。
オーロラは本来のストーリーでは眠れる森の美女(Sleeping Beauty)なので、それを1文字もじった「Beasty」と呼ぶという、メタ的な言葉遊びにもなっていたんですね。この言葉はBeastieと綴ってもいいような気がしますが、あえてBeastyと綴っているのは、Beautyとかけたかったからなのかな、とも思いました。
この気付きには生徒と一緒に感動してしまいました。授業って、こういう思いがけない気付きがあったりするので良いんですよね。
ところで、日本語字幕ではBeastyは「愛しい子」、日本語吹替では「醜い子」となっており、Beastyという言葉がもつ二面性のうちどちらかに寄せた訳になっているようです。
少しまじめなお話もしておきますと、
英語学習を効率よく進めるためには、「精読」「多読多聴」はどちらも重要です。
今回のような映画を観てくる課題というのは、多聴を意識したアプローチです。この学習法はハマれば効果抜群なので、続けていくつもりです。
ただ、その生徒の年齢や現在の英語力によっても、どういった勉強に何割の時間を割くべきか、というのは変わってきます。
英語の教師たるもの、効率的な学習法についての科学的知識をしっかりとアップデートして指導に役立ててこそプロの教師と胸を張って言えると思っています。
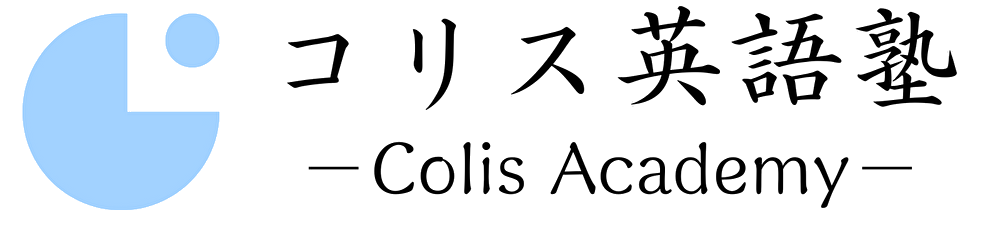





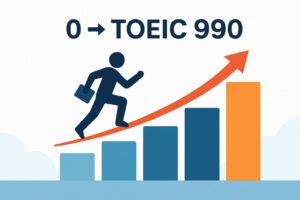


コメント