安河内哲也先生と大岩秀樹先生のご著書です。
中級編、共通テスト・中堅私大レベル、英検2級レベルと書かれています。
授業で改訂版のLESSON01~12までを扱ったので、レビューを書いてみようと思います。
良いところ
- シリーズの特徴として、レベル1~6まであるので段階を踏んで学習がしやすい
- 全ての長文に音声・リスニング動画がついている
- 読んでいて面白い文が多い
特に、音読練習用動画は復習用教材としてとても良いと思います。
この本で勉強するなら、動画での復習はマストでやりたいところです。
また、3の「読んでいて面白い」というのはかなり良いポイントかと思います。個人的に特に面白かったのは、マララ・ユスフザイさんについてのお話です。
面白い文の例
さらに、面白い文の例として、LESSON11にあった以下のようなパラグラフを挙げてみます。
So, one or two drinks may be just what a person needs — or to use an English idiom, “It may be just what the doctor ordered.” But, on the other hand, we can safely say “that even one cigarette is one cigarette too many!”
だから、1,2杯の飲酒はちょうど人が必要な量、つまり、イギリスの慣用句を使って言えば「おあつらえ向きの量」かもしれない。しかし一方では、「1本のたばこでさえ1本多すぎる」と言って差し支えないのである。
この「1本のたばこでさえ1本多すぎる」というのは面白い言い方ですが、生徒にはちょっと伝わりづらいようです。
結局言いたいことは、
「(お酒は1杯くらいならむしろ健康に良いという意見もあるが、)たばこは1本も吸わない方がいい」
ということです。
それを、「たばこは0本が望ましい」→「1本でも(0本と比べると)1本多すぎる」というひねった言い方になっています。
気になるところ
- 音声のダウンロードが少しだけ面倒
- 同じレベル4の1冊の中でも、LESSONごとのレベル差が結構ある
- にもかかわらず、制限時間・目標得点がすべて同じ
- 設問が簡単すぎる(本文を読まなくても常識的に答えが分かってしまう)ものがちらほらある
- 誤訳がある
音声のダウンロードについてですが、「LESSONごとのQRコードがない」「パスワードを入力する必要がある」ということで、若干面倒です。リスニング動画の方がさくっと見られるので、おそらくこっちをメインで考えているのかなというところです。
文章ごとのレベル差についてですが、概ね以下のような印象を持ちました。
- LESSON01…やや難
- LESSON02…ふつう
- LESSON03…ふつう
- LESSON04…簡単
- LESSON05…かなり難
- LESSON06…簡単
- LESSON07…簡単
- LESSON08…ふつう
- LESSON09…ふつう(設問は簡単)
- LESSON10…やや簡単
- LESSON11…やや簡単
- LESSON12…やや簡単
特に、LESSON05が周りのものより難しすぎてびっくりすると思います。
ただ、いろんな難易度の文章を読むこと自体は悪いことではないと思うので、英語学習上そこまで大きな問題になるわけではないと思います。
全体的なレベル感としては、問題文や使われている単語自体は共通テストと同じか、共通テストより若干難しいと思います。
ただ、共通テストの方は設問が紛らわしかったり、時間が足りないという問題があるので、この問題集では点が取れても共通テストでは全然点が取れないということも当たり前のように起こりそうです。
和訳について
生徒にとって解釈が難しそうな文の和訳をいくつか見ていると、ちょっと和訳が怪しい部分があったので、1つ例にとって見ていきます。
LESSON10に、以下のような文があります。
When they(animals) socially learn and develop different ways of doing things, biologists now speak of culture.
該当部分の解説の和訳は以下のようになっています。
動物たちが社会的に学習し、物事を行う異なった方法を発達させるとき、生物学者は今では文化について話す。
どうでしょう、この日本語読んで意味分かりますか?
分からないですよね。私も全く分かりません。笑
私なりにこの方がいいのでは、と思う和訳を直訳調を保ちつつ書いてみると↓
動物たちが社会的に学習し、物事を行うさまざまな方法を身につけるとき、生物学者は今では文化という用語を用いる。
この本の和訳の一番まずいポイントは、speak of~を、「~について話す」と訳しているところです。
これは明確に誤りで、本文のspeak of~は、(珍しい用法ですが)「~という用語を用いる」という意味の表現です。
もう少し意訳するなら↓
動物たちが社会的な学習を通じて、物事を行うさまざまなやり方を身につけることを、生物学者たちは「文化」と呼ぶようになってきている。
総評
全体としては、十分にお勧めできる書籍です。
特に、「面白い文章が多い」「リスニング・シャドーイングの反復練習がしやすい」のが高ポイントです。
英語は「問題を解けば成績が伸びる」わけでは決してないのが、数学などと違うところです。いかに地道な努力を重ねられるかが大事な科目です。
もっというと、努力と思わずに楽しんで勉強できると最強です。
私も(受験学年以外では特に)そのような指導を心がけています。
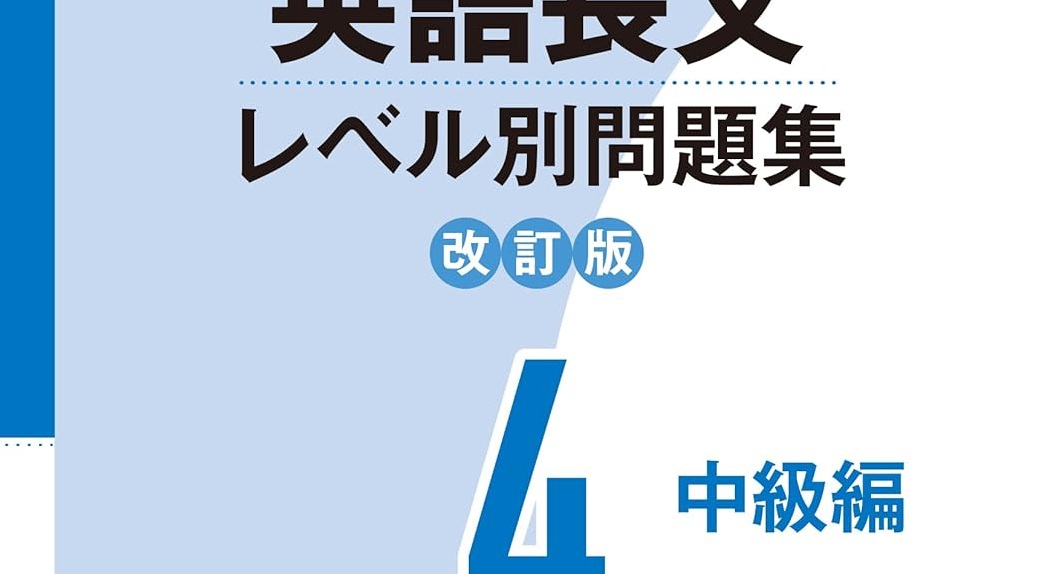



コメント