私立中高一貫の中学校に通いながらも、高校受験で早慶附属に入りたくて外部受験をする子は、過去に私が受け持ってきた生徒にも一定数います。
今日はそんな中でも、課題が多いと有名な国学院久我山中から慶應義塾高校に合格した男の子のお話をご紹介しようと思います。
彼が入塾してきたのは、中2の終わり頃。早慶付属高校を狙って入塾する子としては、遅い方になります。
中学受験で算数を鍛えた経験もあって、数学はやや得意な方。一方、英語や国語はそんなにいい成績ではなかったです。
SAPIXの偏差値では、「50台前半」(※)というのが慶應義塾高校の合格が見えてくる基準の偏差値となりますが、彼の偏差値はだいたい40台を推移していました。
(※)…SAPIX偏差50台前半は、Vもぎの偏差値70くらいになります。
上にも書きましたが、国学院久我山は私立の中でも課題が多いと有名です。
実際に私が見てきた生徒でも、久我山中の子は数名いましたが、みんな忙しそうにしていました。
塾の宿題は何とかこなす(たまに学校の課題が多すぎて塾の宿題に手が回らないこともある)けれども、それ以上の復習や+αの勉強までは手が回らない、そんな印象です。
そういうわけで、久我山中の生徒にはいつも、時間の使い方についてよく質問を受けていました。
「全科目復習していると手が回らないんですけど、何を優先したらいいですか」と。
彼らの場合には本当に時間がないようなので、こちらもそれに合わせて学習計画を一緒に考えてあげる必要があります。
この生徒の場合には、数学は最低限の勉強時間に留めて、可能な限り英語に時間を割くことにしました。
志望校さえはっきり決まっているのであれば、数学はどの学校も出題傾向が決まっているので、学習内容や分野に優先順位をつけることができます。
数学については、優先順位が高い分野・内容に絞って勉強を進めたということです。彼は数学はある程度得意だったことも理由の一つです。
一方、英語には分野もなにもありませんから、英語はしっかりと時間をかけて実力をつけていく必要があります。
こういう指導ができるためには、各高校の入試の傾向を教師側でしっかりと把握しておいたうえで、目の前の生徒をしっかりと観察して何が必要かひとりひとりにあわせて(オーダーメイドで)考える必要がありますね。
ただ、勉強の方針を決めたからといってすぐにうまくいくものではありません。
彼も何度も不安になって相談に来ました。そのたびに、学習の方針を微調整したり、正しい道を歩いているから自信をもって勉強するように伝えたりしていました。
そんなこんなで迎えた入試。
実は、最後まで彼の偏差値は合格80%ラインには届きませんでした。それでも、第一志望の慶應に焦点を当てて勉強してきていますから、可能性はあります。
早慶の前哨戦ともいわれる、立教新座の入試では残念ながら不合格。
しかし、慶應義塾高校には補欠のHから繰り上がり合格しました。補欠Hは過去の実績からするとあまり上がらないですが、その年は繰り上げが多かったようで、上がってくれました。
合格後に挨拶に来てくれたとき、やけに飄々としていたのは今でも印象的ですが(笑)
彼の将来を考えても、高校受験で早慶附属校に合格することのインパクトは極めて大きかったと思います。
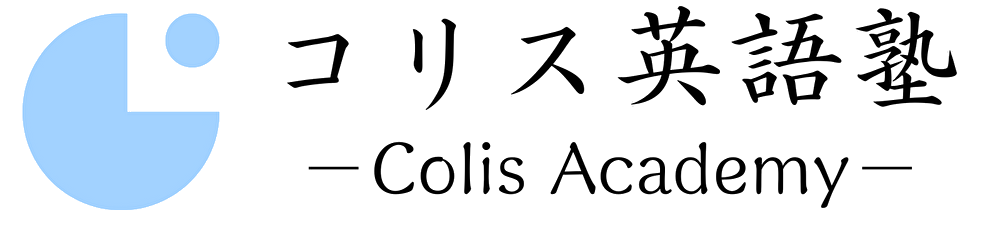

コメント